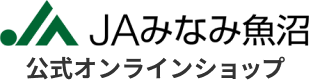日本有数の豪雪地帯であり、最高級コシヒカリの産地として知られる新潟県南魚沼。ここで、農家の情熱と豊かな自然によって育まれる希少なもち米があります。本記事では、市場流通わずか1%と言われる「南魚沼産こがねもち」の隠れた魅力をご紹介。厳しい環境が生んだ極上の味わいから、地元ならではの美味しい食べ方、そして生産者のあくなきこだわりまで、南魚沼の食文化とともにその真髄をお届けします。
豪雪が育む銘産地。「日本一の米処」南魚沼から

もち本来の旨みを持ち、コシの強さが特徴のもち米・南魚沼産こがねもちは、米どころとして知られる新潟県南魚沼で限られた農家のみで栽培されています。南魚沼は、新潟県の南端に位置し、東は八海山をはじめとする越後山脈、西は魚沼丘陵を望む四方を山々に囲まれる中山間地です。雪どけ水による水源に恵まれ、良質米の産地として知られています。
この、日本有数の豪雪地帯としても有名な南魚沼が、米栽培の一大産地となるための道のりは大変険しいものだったと伝えられます。新潟県を代表するコシヒカリは、昭和31年に新潟県の奨励品種に採用されたにも関わらず、倒れやすく、いもち病に弱かったため、県内の大稲作地帯では魅力のない品種と扱われたそうです。
しかし、南魚沼の農家たちは一貫してコシヒカリの栽培を続け、栽培技術の向上によってコシヒカリの欠陥を克服し、機械性能の改善によって安定した米づくりが可能となりました。また、雪国ならではのスキー需要の高まりから、民宿でふるまわれたコシヒカリが評価を得て、関東圏を中心にコシヒカリの知名度が増していきました。60年にわたる農家の栽培努力と、雪国に埋もれた良食味の逸品を民宿や観光産業が大きくアピールし、南魚沼を米の一大産地へと育てました。
具だくさんの「越後雑煮」と、空を舞う祝餅「もちまき」の記憶

この「南魚沼産こがねもちシングルパック」は、南魚沼で栽培された新米の南魚沼産こがねもちを100%原料とした切りもちです。また、1個1個が個別に包装されているため、美味しさそのままに、長期間の保存が可能です。
とは言っても、賞味期限は製造日から11カ月ですが…。
僕らが暮らす南魚沼では、主にお正月のごちそうとして切りもちを食べています。「きな粉もち」や「小豆もち」もありますが、お勧めは伝統の郷土料理「雑煮」です。新潟県の雑煮はその名前のように、いろいろな具材をたくさん入れて、お椀の中をいっぱいにするもち雑煮です。地域によって具材が異なりますが、我が家の雑煮は長細く切った大根と人参、ごぼう、サトイモ、コンニャク、豆腐、鮭と野菜が盛りだくさん。最後の仕上げにイクラをのせて、さっぱり醤油味の雑煮の出来上がりです。
元旦に食べる雑煮は正月を実感できる逸品でいつになく美味しく思えるのですが、1月3日になると毎日食べ続けているため、ラーメンなんかが愛おしく思えるときもあります…。
購入はこちらから
南魚沼産こがねもち シングルパック
杵つき製法で搗き上げたこのお餅は、粘りとこしが強く、 香りと食味も良いと好評いただいており、多くの方からリピート注文をいただいております。 JAみなみ魚沼自慢のお米やお餅は、ギフトや贈答品としても大変喜ばれます。 お世話になった方や遠方の親族へ贈ってみてはいかがでしょうか。 もちろんご自宅用にもおススメ。美味しいお餅をどうぞお楽しみください。 包装は保存に強く便利な個包装です。
南魚沼産こがねもち シングルパック¥600g×2袋 2,000〜
送料無料
みなみ魚沼公式ECで購入する>
また、切りもちは食べる食品だけでなく、新築時のもちまきにも使用しています。
南魚沼では、建築途中で行う上棟式を「建て前」などと呼び、近所やとなり村の人たちに声をかけ、もちまきを実施します。「なぜ、もちをまくのだろう?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、一説によると「その建物のお披露目と家内安全を願って、周囲の方々に祝いもちをまき、近所づきあいを深める行事」とされています。
我が家も7年前に新築した際は、もちと五円玉、野菜などをまいた記憶があります。まくもちの量は、末広がりの「八」にちなんで、8升分の切りもちをまきました。また、施主(親父)がまいた天もちは1升もちと超巨大なもち…。今、冷静に考えると集まった人の頭に当たろうものなら、大けが・大参事になっていたかもなんて思ったりもします。
また、近年は、もちまきを実施する方が少なくなり、昭和の行事的な感じとなってしまいました。もちまきには、それなりのお金がかかるため、同然なのかもしれません…。
流通量はわずか1%。栽培の難しさと「水・杵つき」へのあくなきこだわり

さて、この「南魚沼産こがねもち」はどのようにつくられているのでしょうか?
実は、原料のこがねもち栽培は非常に難しいといわれているため、栽培する農家はごくまれなんです。コシヒカリと比べ、稲の穂が顔を出す「出穂」が1週間ほど早く、夏場の高温障害を受けやすい品種となります。また、実の入りも早く、鳥などの獣害が多いため、栽培される農家はこだわりと誇りを持って農作業に汗を流しています。令和1年産の集荷数量は、お米全体の集荷数量の約1%程度となっています。そのため、南魚沼で栽培されるもち米が市場に出回らず、希少と言われる由縁はこの現状が大きく影響しています。

この希少で、さらに新米100%を原料にした「シングルパック」は、魚沼市の株式会社ゆのたにの切りもち専用工場で製造されています。切りもちの製造工程は、まず、もち米を削るところから始まります。88%以下を目安に、もち米の表面を削り、あわせて土壌菌も削り取っています。また、もち米を浸漬する水は、ゆのたに地域の豊富な伏流水。溜め水と異なり、100%の天然水を掛け流すことで、もち米に含まれる雑味が抜け、旨みが増すなどとも言われています。
コシの強さは、杵つき方式。杵が100回~110回つき固めることで、煮崩れしないコシの強い切りもちが完成します。
「米・水・技」の結晶。南魚沼の美味を、いま食卓へ

切りもちは「もち米」と「水」だけでつくられる極めてシンプルな食品です。もち米、そのものが旨くなければ、美味しい切りもちはできません。また、旨いもち米を加工する、専用のもち製造工場がなければ、これもまた、美味しい切りもちはできません。
米づくりに適した南魚沼の気候風土と、こだわりを持ってもち米を栽培する農家の努力が甘く旨みのあるもち米を育て、豊富な天然の伏流水を活用し、クリーンな環境で製造された切りもちは、雑菌に弱い切りもちを美味しさそのままに、消費者の皆さまにお届けすることを可能にしました。
この、人と自然と施設がおりなす南魚沼の美味を、いつ食べるの?今でしょ!
お後がよろしいようで…ご清聴、誠にありがとうございました。
購入はこちらから
南魚沼 豊穣セット(米・もち)
人気No.1商品の「南魚沼産こしひかり」と、 新米のもち米で搗いた「南魚沼産こがねもち シングルパック」のセット商品! 南魚沼の“おいしい”をご堪能ください。 JAみなみ魚沼自慢のお米やお餅やは、ギフトや贈答品としても大変喜ばれます。 ご自宅用はもちろん、御歳暮にもぜひご利用ください。
南魚沼 豊穣セット(米・もち) | 【お歳暮冬ギフト】魚沼コシヒカリ発祥の地・南魚沼から令和7年産新米コシヒカリ・餅をお届け!JAみなみ魚沼公式オンラインショップ¥6,300〜
送料無料
みなみ魚沼公式ECで購入する>