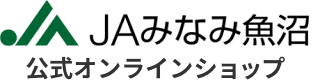私たちの食事に欠かせない、主食として親しまれているお米。しかし、お米を美味しく炊くのは意外と難しいものです。炊飯器さえあれば簡単に炊けるように思われがちですが、実はお米の種類や研ぎ方、水の加減など、いくつもの要素が影響します。
お米を美味しく炊くためには、正しい炊飯の手順を知っておくことが大切です。この記事では、お米を美味しく炊くための基本的な知識を解説していきます。ぜひ最後までチェックして、美味しいご飯作りに役立ててくださいね◎
お米の基本の炊き方
まずは、お米の基本の炊き方を紹介します。
- お米用の計量カップ(1カップ=1合=180ml=150g)で必要な分量を計ります。
- たっぷりの水で米を素早く2~3回かき混ぜ、水をすぐに捨てます。これを水がほぼ透明になるまで2~3回繰り返します。
- 洗い終わった米に適量の水(目安は米1合につき水1.1〜1.3倍)を加え、30分から2時間ほど浸して吸水させます。
- 浸水後、炊飯器のスイッチを入れてお米を炊きます。
- 炊き上がったら10〜15分ふたを開けずに蒸らし、余熱でふっくらさせます。
- 蒸らし終えたらご飯を底からやさしくほぐし、お茶碗にふんわりとよそって完成です。
炊飯器は火加減の調節いらずで、手軽にお米を炊くことができます。一人暮らしなら、3合炊きなど容量が小さめのものでも十分なお米を炊くことができます。最近では、一人暮らし用でも「しゃっきり」「もっちり」など、好みの硬さに炊ける炊飯器も増えています。
また、メーカーによっては炊飯時間に「蒸らし」の工程が含まれているものもあるため、自宅の炊飯器の説明書を確認し、蒸らし工程が含まれている場合は、手順5を省いても問題ありません。
購入はこちらから
南魚沼産こしひかり 精米(2kg・5kg)
JAみなみ魚沼イチオシのお米を産地直送でお届け!魚沼産コシヒカリの中でも特に美味しいと評価されてる『南魚沼産コシヒカリ』。豊富な雪解け水や昼夜の寒暖差に恵まれた南魚沼の自然環境は、ふっくらもちもちで旨みと甘みの強いコシヒカリを生み出します。味わいと品質にこだわった産地自慢のお米をぜひご賞味ください!
南魚沼産こしひかり 精米(2kg・5kg)¥1820〜
送料無料
みなみ魚沼公式ECで購入する>
美味しく炊くコツと失敗しないポイント
ここからは、炊飯器を使わず、鍋や土鍋でお米を炊く方法を紹介します。鍋や土鍋は炊飯器と違って火加減の調整など必要なポイントがあるので、しっかりおさえておきましょう!
お米の計量は丁寧に
お米を炊く際、計量はとても重要です。お米の量が正しく測れていないと水加減もずれ、芯が残ってしまったり、べちゃっとした食感になってしまいます。計量カップにはお米専用の180mlのタイプと調理用の200mlのタイプがあるので、目盛りをよく確認して使用してください。お米は180mlの計量カップを使用すると、すりきり1杯でちょうど1合分になります。
まずは、計量カップにお米を山盛り入れ、菜箸などを使ってすりきります。慣れてくると、はじめからすりきり一杯を入れられるようになりますが、慣れないうちはこの方法で測ると失敗しにくいですよ◎
浸水の意味と時間の目安
浸水は、お米を美味しく炊くために欠かせない手順です。適切な時間お米を水に浸すことで、お米のでんぷん質がアルファ―化(糊化)し、旨味が引き出されます。
浸水時間が長すぎると、でんぷん質が溶け出してべたつきの原因となります。一方、浸水時間が短すぎるとお米が十分にアルファ―化できず、旨味が引き出せません。
新米は収穫されて間もないため水分量が多く、普通のお米より浸水時間が短くて済みます。お米の種類ごとに適切な時間だけ浸水させることで、お米がふっくら膨れ上がり、旨味が引き出された美味しいご飯が炊けるのです。
浸水時間の目安は、夏なら約30分、春・秋なら40〜50分、冬なら1〜2時間ほどです。ミネラルウォーターなど、良質な水を使用するとさらに旨みや風味が際立ちますよ。
お米は手早く研ぐ
お米を研ぐときは、できるだけ手早く研ぎましょう。あまり時間をかけて洗うと、お米が割れたり、旨み成分が流れ出たりしてしまいます。力を入れすぎず、優しく全体を混ぜるように洗うのがポイントです。
お米が適切に研がれているかどうかは、経験によってだんだんと見極められるようになりますが、慣れないうちは水の色で判断するのがおすすめです。お米を研いだ水がうっすら透き通り、やや白っぽさが残っている程度が適切な研ぎ加減です。水が完全に透き通るまで研ぐ必要はないので、1回研ぐごとに水の様子をチェックしてみましょう。
お米の種類によって水加減を変える
お米には、普通の精米、無洗米、新米の3種類があります。これらの種類によって、適切な水加減が異なります。
| 白米の種類 | 水加減の目安 |
|---|---|
| 普通精米 | お米1合(150g)に対し、200ml前後の水を入れる |
| 無洗米 | お米1合に対し、230ml前後の水を入れる |
| 新米 | お米1合に対し、190ml前後の水を入れる |
普通精米(洗うお米)の場合、1合(150g)に対して200mlの水を使用するのが基本です。一方、無洗米はぬかが取り除かれていることから米の粒が小さく、1合に含まれる米粒の数が多くなっているため、普通精米よりも水を多めにする必要があります。1合(150g)に対して230mlの水を使用するのが目安です。
また、新米は水分を多く含んでいるため、普通精米よりも水を少なめにするのが一般的です。目安としては1合(150g)に対して水190mlとなりますが、計量しにくい場合は普通精米の水の分量から大さじ1程度水を減らす方法もあります。
このように、白米の種類によって水加減が変わるため、炊飯前に適切な水加減を把握しておくことが大切です。
炊き上がりのご飯の目安量
お米を炊く際は、炊き上がりの量についても把握しておきたいですよね。お米1合(約150g)を炊くと、炊き上がったご飯の量は約330g〜350gになります。これは生のお米の約2〜2.3倍の量に相当し、一般的なお茶碗1杯分(約150g)で計算すると、1合のご飯は約2杯分になります。つまり、お米1合で炊いたご飯は約2人分の量となります。
しかし、炊き上がりのご飯の量は水加減によって若干異なり、人数分はご飯はお茶碗の大きさや盛り方によっても変わります。お米を無駄にしないためにも、ご家庭の事情や用途に合わせて、適切な分量を炊くことが大切です。
まとめ
お米を美味しく炊くためには、お米の量や水加減を正確に測ることと、十分な浸水時間を確保することが大切です。お米の種類や季節に合わせて適切に浸水させることで、お米がふっくらと膨らみ、旨味も引き出されます。
また、研ぎすぎに注意しつつ、手早く洗うのもポイントです。研ぎすぎはベタつきの原因になりますので、水の色を確認しながら、適切に研ぐよう心がけましょう。毎日食べるお米だからこそ、炊き方のコツをおさえて、無駄なく美味しく炊飯しましょう。
購入はこちらから
南魚沼産こしひかり 精米(2kg・5kg)
JAみなみ魚沼イチオシのお米を産地直送でお届け!魚沼産コシヒカリの中でも特に美味しいと評価されてる『南魚沼産コシヒカリ』。豊富な雪解け水や昼夜の寒暖差に恵まれた南魚沼の自然環境は、ふっくらもちもちで旨みと甘みの強いコシヒカリを生み出します。味わいと品質にこだわった産地自慢のお米をぜひご賞味ください!
南魚沼産こしひかり 精米(2kg・5kg)¥1820〜
送料無料
みなみ魚沼公式ECで購入する>